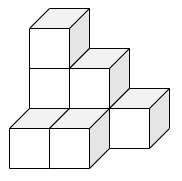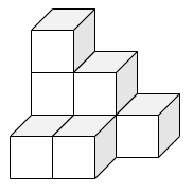バーンサイドの補題が競技プログラミング界隈で話題のようです。先日開催された ABC で出題されたからです。
https://atcoder.jp/contests/abc198/tasks/abc198_f
この記事の目標は、バーンサイドの補題を表現論を用いて証明することです。最近表現論を勉強しているので、そのアウトプットを兼ねています。
バーンサイドの補題
#
バーンサイドの補題 (コーシー・フロベニウスの補題とも呼ばれます) は次のような命題です。
G G G σ : G → S X \sigma\colon G\to S_X σ : G → S X m m m
m = 1 ∣ G ∣ ∑ g ∈ G ∣ Fix ( g ) ∣
m=\frac{1}{|G|}\sum_{g\in G}|\text{Fix}(g)|
m = ∣ G ∣ 1 g ∈ G ∑ ∣ Fix ( g ) ∣ で求められる。
ここで ∣ G ∣ |G| ∣ G ∣ G G G Fix ( g ) = { x ∈ X ∣ σ g ( x ) = x } \text{Fix}(g)=\{x\in X\mid \sigma_g(x)=x\} Fix ( g ) = { x ∈ X ∣ σ g ( x ) = x } g g g X X X S X S_X S X X X X X X X 作用 とは群準同型 σ : G → S X \sigma\colon G\to S_X σ : G → S X x ∈ X x\in X x ∈ X x x x 軌道 とは集合 G ⋅ x = { σ g ( x ) ∣ g ∈ G } G\cdot x=\{\sigma_g(x)\mid g\in G\} G ⋅ x = { σ g ( x ) ∣ g ∈ G } X X X X X X
具体例を 1 つ考えましょう。n n n X X X n n n ∣ X ∣ = n ! |X|=n! ∣ X ∣ = n ! G G G n n n G G G X X X 1 , 2 , … , n 1,2,\ldots,n 1 , 2 , … , n 2 , … , n , 1 2,\ldots,n,1 2 , … , n , 1 X X X G G G
Fix ( g ) = { 0 ( g ≠ id ) ∣ X ∣ = n ! ( g = id )
\text{Fix}(g)=\begin{cases}
0 & (g\ne \text{id}) \\
|X|=n! & (g=\text{id})
\end{cases}
Fix ( g ) = { 0 ∣ X ∣ = n ! ( g = id ) ( g = id ) となります。よって、答えはバーンサイドの補題から、m = n ! n = ( n − 1 ) ! m=\frac{n!}{n}=(n-1)! m = n n ! = ( n − 1 )!
また、回転や裏返しで一致するものを同一視するとき、群 G G G 2 n 2n 2 n m = n ! 2 n = ( n − 1 ) ! 2 m=\frac{n!}{2n}=\frac{(n-1)!}{2} m = 2 n n ! = 2 ( n − 1 )!
表現論の基礎
#
バーンサイドの補題を証明するために、表現論の基礎を準備します。ここで書くことはとても基本的なもので、どの表現論の本にも載っていると思います。なので証明は省略します。
群は対称性の研究 (特に方程式の解の対称性) から生まれました。対称性という具体的なものから、群の公理という抽象的なものが生まれたわけです。
逆に、与えられた (抽象的な) 群に対して、どういった空間の対称性を表すかを考えるといったこともよく行われます。この 1 つが上でも述べた作用です。作用は群の各元に対し、集合 X X X
X X X V V V V V V G L ( V ) GL(V) G L ( V ) G → S V G\to S_V G → S V G → G L ( V ) G\to GL(V) G → G L ( V ) 表現 といいます。改めて書くと、G G G V V V G → G L ( V ) G\to GL(V) G → G L ( V )
1 つ自明な例をあげます。任意の g ∈ G g\in G g ∈ G φ g \varphi_g φ g V V V φ : G → G L ( V ) \varphi\colon G\to GL(V) φ : G → G L ( V ) V V V 自明な表現 といいます。
線形変換は適当に基底を選ぶことで行列にすることができます。よって G L ( V ) GL(V) G L ( V ) G L n ( C ) GL_n(\mathbb{C}) G L n ( C ) n n n V V V φ : G → G L n ( C ) \varphi\colon G\to GL_n(\mathbb{C}) φ : G → G L n ( C ) g ∈ G g\in G g ∈ G φ g \varphi_g φ g χ ( g ) \chi(g) χ ( g )
χ ( g ) = Tr ( φ g ) = ∑ i = 1 n ( φ g ) i i
\chi(g)=\text{Tr}(\varphi_g)=\sum_{i=1}^n(\varphi_g)_{ii}
χ ( g ) = Tr ( φ g ) = i = 1 ∑ n ( φ g ) ii とします。このようにして定まる写像 χ : G → C \chi\colon G\to \mathbb{C} χ : G → C 指標 といいます。もともと n n n 「2 つの表現が同値であるための必要十分条件は、それらの指標が一致することである」 という定理が成り立ちます。指標は表現の本質であり、指標によって表現がわかってしまいます。これが表現論のすごいところですね。
表現が同値であることの定義をまだしていませんでした。φ : G → G L ( V ) , ψ : G → G L ( W ) \varphi\colon G\to GL(V),\psi\colon G\to GL(W) φ : G → G L ( V ) , ψ : G → G L ( W ) φ , ψ \varphi,\psi φ , ψ 同値 であるとは、線形同型 T : V → W T\colon V\to W T : V → W g ∈ G g\in G g ∈ G T ∘ φ g = ψ g ∘ T T\circ\varphi_g=\psi_g\circ T T ∘ φ g = ψ g ∘ T
2 つの表現 φ : G → G L ( V ) , ψ : G → G L ( W ) \varphi\colon G\to GL(V), \psi\colon G\to GL(W) φ : G → G L ( V ) , ψ : G → G L ( W ) ρ : G → G L ( V ⊕ W ) \rho\colon G\to GL(V\oplus W) ρ : G → G L ( V ⊕ W ) ρ g ( v , w ) = ( φ g ( v ) , ψ g ( w ) ) ( g ∈ G , v ∈ V , w ∈ W ) \rho_g(v,w)=(\varphi_g(v),\psi_g(w)) \ (g\in G, v\in V, w\in W) ρ g ( v , w ) = ( φ g ( v ) , ψ g ( w )) ( g ∈ G , v ∈ V , w ∈ W ) 直和 といい、ρ = φ ⊕ ψ \rho=\varphi\oplus\psi ρ = φ ⊕ ψ φ g \varphi_g φ g V V V φ : G → G L ( V ) \varphi\colon G\to GL(V) φ : G → G L ( V ) dim V \dim V dim V
φ : G → G L ( V ) \varphi\colon G\to GL(V) φ : G → G L ( V ) W W W V V V W W W G G G g ∈ G , w ∈ W g\in G, w\in W g ∈ G , w ∈ W φ g ( w ) ∈ W \varphi_g(w)\in W φ g ( w ) ∈ W V V V { 0 } \{0\} { 0 } V V V G G G G G G 既約表現 であるといいます。
整数論においては素数が重要な役割を果たします。これはすべての整数が素数の積として表すことができ、かつその表し方が一意であるからです。実は表現論においても似たことが成り立ちます。表現論においては既約表現が素数と同じような役割を果たします。
マシュケの定理 : 有限群の表現はすべていくつかの既約表現の直和と同値である。
よって任意の表現 φ \varphi φ φ 1 , φ 2 , … \varphi_1,\varphi_2,\ldots φ 1 , φ 2 , … φ 1 ⊕ m 1 ⊕ φ 2 ⊕ m 2 ⊕ ⋯ \varphi_1^{\oplus m_1}\oplus\varphi_2^{\oplus m_2}\oplus\cdots φ 1 ⊕ m 1 ⊕ φ 2 ⊕ m 2 ⊕ ⋯ m i m_i m i 重複度 といいます。指標を考えましょう。既約表現の指標を既約指標 といいます。φ \varphi φ χ \chi χ φ i \varphi_i φ i χ i \chi_i χ i χ = m 1 χ 1 + m 2 χ 2 + ⋯ \chi=m_1\chi_1+m_2\chi_2+\cdots χ = m 1 χ 1 + m 2 χ 2 + ⋯ m i m_i m i
⟨ χ , χ ′ ⟩ = 1 ∣ G ∣ ∑ g ∈ G χ ( g ) ‾ χ ′ ( g )
\langle \chi,\chi^{\prime}\rangle=\frac{1}{|G|}\sum_{g\in G}\overline{\chi(g)}\chi^{\prime}(g)
⟨ χ , χ ′ ⟩ = ∣ G ∣ 1 g ∈ G ∑ χ ( g ) χ ′ ( g ) これが指標の内積です。すると、次の素晴らしい関係が成り立ちます。
指標の第一直交性 : χ 1 , χ 2 , … \chi_1,\chi_2,\ldots χ 1 , χ 2 , …
⟨ χ i , χ j ⟩ = { 1 ( i = j ) 0 ( i ≠ j )
\langle \chi_i,\chi_j\rangle=\begin{cases}
1 & (i=j) \\
0 & (i\ne j)
\end{cases}
⟨ χ i , χ j ⟩ = { 1 0 ( i = j ) ( i = j ) が成り立つ。
つまり、既約指標は正規直交します。このことから、重複度は m i = ⟨ χ , χ i ⟩ m_i=\langle \chi,\chi_i\rangle m i = ⟨ χ , χ i ⟩ m i m_i m i
置換表現
#
σ : G → S X \sigma\colon G\to S_X σ : G → S X C X \mathbb{C}X C X X X X X X X X X X C X \mathbb{C}X C X g ∈ G g\in G g ∈ G σ g \sigma_g σ g σ ~ g \widetilde{\sigma} _ g σ g
σ ~ g ( ∑ x ∈ X c x x ) = ∑ x ∈ X c x σ g ( x )
\widetilde{\sigma} _ g(\sum_{x\in X}c_xx)=\sum_{x\in X}c_x\sigma_g(x)
σ g ( x ∈ X ∑ c x x ) = x ∈ X ∑ c x σ g ( x ) となります。このようにして表現 σ ~ : G → G L ( C X ) \widetilde{\sigma}\colon G\to GL(\mathbb{C}X) σ : G → G L ( C X ) 置換表現 といいます。
置換表現も既約表現に分解できます。このとき、自明な表現の重複度を考えることで、バーンサイドの補題を証明します。
χ 1 \chi_1 χ 1
m 1 = ⟨ χ 1 , χ σ ~ ⟩ = 1 ∣ G ∣ ∑ g ∈ G χ 1 ( g ) ‾ χ σ ~ ( g ) = 1 ∣ G ∣ ∑ g ∈ G χ σ ~ ( g )
m_1=\langle\chi_1,\chi_{\widetilde{\sigma}}\rangle=\frac{1}{|G|}\sum_{g\in G}\overline{\chi_1(g)}\chi_{\widetilde{\sigma}}(g)=\frac{1}{|G|}\sum_{g\in G}\chi_{\widetilde{\sigma}}(g)
m 1 = ⟨ χ 1 , χ σ ⟩ = ∣ G ∣ 1 g ∈ G ∑ χ 1 ( g ) χ σ ( g ) = ∣ G ∣ 1 g ∈ G ∑ χ σ ( g ) となります。
補題 1 :χ σ ~ ( g ) = ∣ Fix ( g ) ∣ \chi_{\widetilde{\sigma}}(g)=|\text{Fix}(g)| χ σ ( g ) = ∣ Fix ( g ) ∣
証明:X = { x 1 , … , x n } X=\{x_1,\ldots,x_n\} X = { x 1 , … , x n } X X X σ ~ g \widetilde{\sigma} _ g σ g A A A
A i j = { 1 x i = σ g ( x j ) 0 x i ≠ σ g ( x j )
A_{ij} = \begin{cases}
1 & x_i=\sigma_g(x_j) \\
0 & x_i\ne \sigma_g(x_j)
\end{cases}
A ij = { 1 0 x i = σ g ( x j ) x i = σ g ( x j ) となります。特に
A i i = { 1 x i ∈ Fix ( g ) 0 x i ∉ Fix ( g )
A_{ii} = \begin{cases}
1 & x_i\in\text{Fix}(g) \\
0 & x_i\not\in\text{Fix}(g)
\end{cases}
A ii = { 1 0 x i ∈ Fix ( g ) x i ∈ Fix ( g ) となります。よって、χ σ ~ ( g ) = Tr ( A ) = ∣ Fix ( g ) ∣ \chi_{\widetilde{\sigma}}(g)=\text{Tr}(A)=|\text{Fix}(g)| χ σ ( g ) = Tr ( A ) = ∣ Fix ( g ) ∣
これで
m 1 = 1 ∣ G ∣ ∑ g ∈ G ∣ Fix ( g ) ∣
m_1=\frac{1}{|G|}\sum_{g\in G}|\text{Fix}(g)|
m 1 = ∣ G ∣ 1 g ∈ G ∑ ∣ Fix ( g ) ∣ がわかりました。あとは m 1 m_1 m 1
表現 φ : G → G L ( V ) \varphi\colon G\to GL(V) φ : G → G L ( V ) V G = { v ∈ V ∣ ∀ g ∈ G , φ g ( v ) = v } V^G=\{v\in V\mid \forall g\in G, \varphi_g(v)=v\} V G = { v ∈ V ∣ ∀ g ∈ G , φ g ( v ) = v } G G G
補題 2 :m 1 = dim ( C X ) G m_1=\dim(\mathbb{C}X)^G m 1 = dim ( C X ) G
証明:σ ~ \widetilde{\sigma} σ φ 1 ⊕ m 1 ⊕ φ 2 ⊕ m 2 ⊕ ⋯ \varphi_1^{\oplus m_1}\oplus \varphi_2^{\oplus m_2}\oplus\cdots φ 1 ⊕ m 1 ⊕ φ 2 ⊕ m 2 ⊕ ⋯ φ 1 \varphi_1 φ 1 C X \mathbb{C}X C X V 1 ⊕ m 1 ⊕ V 2 ⊕ m 2 ⊕ ⋯ V_1^{\oplus m_1}\oplus V_2^{\oplus m_2}\oplus\cdots V 1 ⊕ m 1 ⊕ V 2 ⊕ m 2 ⊕ ⋯ ( C X ) G = ( V 1 G ) ⊕ m 1 ⊕ ( V 2 G ) ⊕ m 2 ⊕ ⋯ (\mathbb{C}X)^G=(V_1^G)^{\oplus m_1}\oplus(V_2^G)^{\oplus m_2}\oplus\cdots ( C X ) G = ( V 1 G ) ⊕ m 1 ⊕ ( V 2 G ) ⊕ m 2 ⊕ ⋯ V i G V_i^G V i G V i V_i V i G G G φ i \varphi_i φ i V i G V_i^G V i G { 0 } \{0\} { 0 } V i V_i V i i ≥ 2 i\ge 2 i ≥ 2 φ i \varphi_i φ i V i G = { 0 } V_i^G=\{0\} V i G = { 0 } ( C X ) G = V 1 ⊕ m 1 (\mathbb{C}X)^G=V_1^{\oplus m_1} ( C X ) G = V 1 ⊕ m 1 dim ( C X ) G = m 1 \dim(\mathbb{C}X)^G=m_1 dim ( C X ) G = m 1
補題 3 :dim ( C X ) G \dim(\mathbb{C}X)^G dim ( C X ) G
証明:軌道を O 1 , … , O m \mathcal{O} _ 1,\ldots,\mathcal{O} _ m O 1 , … , O m v i = ∑ x ∈ O i x ∈ C X v_i=\sum_{x\in\mathcal{O} _ i}x\in\mathbb{C}X v i = ∑ x ∈ O i x ∈ C X v i ∈ ( C X ) G v_i\in(\mathbb{C}X)^G v i ∈ ( C X ) G X X X C X \mathbb{C}X C X v 1 , … , v m v_1,\ldots,v_m v 1 , … , v m v 1 , … , v m v_1,\ldots,v_m v 1 , … , v m ( C X ) G (\mathbb{C}X)^G ( C X ) G v = ∑ x ∈ X c x x v=\sum_{x\in X}c_xx v = ∑ x ∈ X c x x ( C X ) G (\mathbb{C}X)^G ( C X ) G y , z ∈ X y,z\in X y , z ∈ X g ∈ G g\in G g ∈ G z = σ g ( y ) z=\sigma_g(y) z = σ g ( y )
v = σ ~ g ( v ) = ∑ x ∈ X c x σ g ( x )
v=\widetilde{\sigma} _ g(v)=\sum_{x\in X}c_x\sigma_g(x)
v = σ g ( v ) = x ∈ X ∑ c x σ g ( x ) となります。左辺の z z z c z c_z c z z z z c y c_y c y c y = c z c_y=c_z c y = c z c 1 , … , c m ∈ C c_1,\ldots,c_m\in\mathbb{C} c 1 , … , c m ∈ C x ∈ O i x\in\mathcal{O} _ i x ∈ O i c x = c i c_x=c_i c x = c i
v = ∑ x ∈ X c x x = ∑ i = 1 m c i v i
v=\sum_{x\in X}c_xx=\sum_{i=1}^mc_iv_i
v = x ∈ X ∑ c x x = i = 1 ∑ m c i v i となります。よって v 1 , … , v m v_1,\ldots,v_m v 1 , … , v m ( C X ) G (\mathbb{C}X)^G ( C X ) G
以上の結果から、バーンサイドの補題が証明できました。
参考文献
#
桂利行, 『代数学II 環上の加群』, 東京大学出版会, 2007
Steinberg, Benjamin. Representation theory of finite groups: an introductory approach . Springer Science & Business Media, 2011.